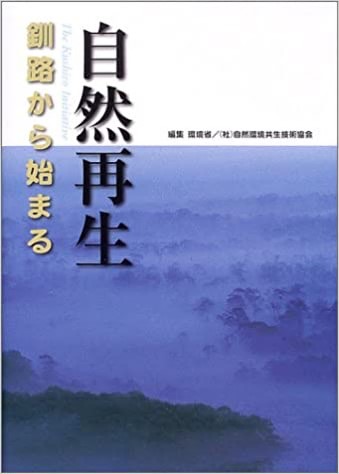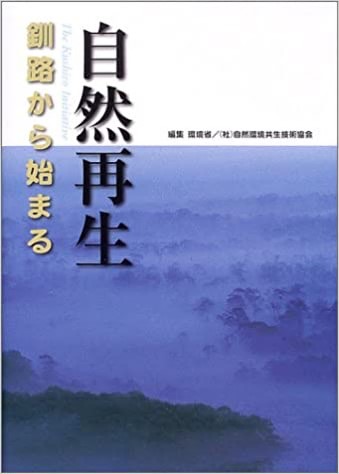自然再生事業には「保全」から「創出」までいくつかのステージがありますが、現地の状況にあわせてそれらを効果的に使い分け・組み合わせて実施されます。事業はできるだけ自然の回復力に委ねるかたちで実施され、科学的なデータに基づいて様々な評価や判断がなされます。
湿原生態系は様々な生態系のなかでも特に消失率が高く劣化も激しいことから、国が主導する国内初の自然再生事業の対象となりました。湿原の象徴でもある釧路湿原が事業地に選定され、その辺縁部にあたる広里地区で先導的に再生事業が始まりました。まずは劣化状況に関する調査が行われ、過去の河川流路切り替え工事に起因する深刻な乾燥化が現地で生じていることが明らかとなりました。その対策として、湿原への河川水供給や湿原からの排水阻止を目的とした事業提案がなされました。しかし、それらの事業を通じた人間活動(漁業や農業)への悪影響が懸念されるなど、広里地区では様々な困難が立ちはだかり再生事業が進むことなく終焉となりました。
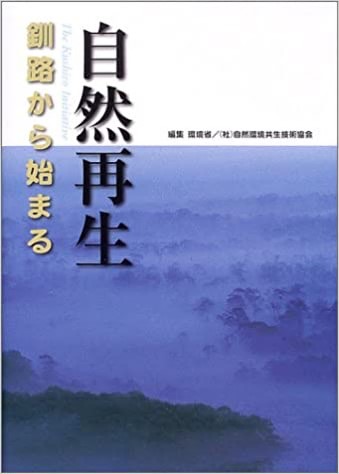


釧路湿原広里地区の湿原再生試験地
比較的小規模の自然再生事業ですが、北海道能取湖畔の塩湿地で行われたアッケシソウ群生地の再生は成功事例の一つとして知られています。秋に赤く紅葉し赤い絨毯のような景観で知られる能取湖のアッケシソウ群生地は、不適切な管理(盛り土等)が原因で一度全滅してしまいました。観光地でもあった群生地の再生を強く求める地元の声に応えるかたちで事業が始まり、状況把握調査・原因解析・対策工事が行われました。全滅の原因は、盛り土に使用された浚渫土が乾燥し極度の酸性土壌が生じたことにありました。土壌の乾燥を回避し中和するために湖水の引き込みや地盤の掘り下げを行い、約5年間かけてもとの群生地へと無事再生しました。


能取湖のアッケシソウ群生地の再生

地盤の掘り下げ

再生事業で復活したアッケシソウ
ここで取り上げた二つの自然再生事業は対照的な結末となりましたが、事業の成否を決める重要なポイントは、周辺の人間活動に対する干渉程度や地域住民の意向なのかもしれません。